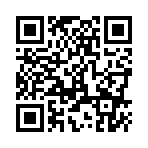2010年08月31日
福済寺と聖福寺 2010年長崎旅行(24)

二年前に長崎を訪れた時は
最後の時間をこの二つの寺の間を歩いた
長崎駅からほど近く、特に聖福寺の情感がよい

この二つの寺院は近い
二年前に書いた記事では案内標識の所用距離の差から「70m」と記したが
実際には200m余り離れているようだ
それでも近いと思う
その「200m」間に一つの境界線があることも二年前の記事に書いた 続きを読む
2010年08月31日
長崎駅 2010年長崎旅行(23)

長崎の町には正味3日間いた
しかし、佐世保から平戸、五島と続いた強行軍に近い日程から来た疲れと
それまでの好天の反動のようなぐずついた天候から
街中をあくせくと歩き回ることはせず
興味のある所、再び訪れてみたい所を思い出したように行ったに過ぎない
急いで周れば1日で済みそうな数だろう
有名な観光地、グラバー園や出島さへ行かなかった
それ故、三日間費やしたにもかかわらず長崎を網羅したには程遠い滞在だったが
訪れた場所のうちの何箇所かを、気の向くままに書き留めてみたい


今回の旅行は、長期間にわたった割にはJR鉄道線のお世話になることは少なかった
今までJR線を使って訪れた長崎も今回はバスで入り、結果的にはバスで去ることになる
そのため頭端式の特徴あるホームに降り立つ事もなかった
しかし街を周る起点としては、どのような旅行形態でも大切な場所になる
続きを読む
2010年08月30日
長崎のゴマ豆腐は甘い(「一休み」の話題) 2010年長崎旅行(22)
土地には土地の味覚がある
長崎にも当然独特の味覚があるのだろう
その中で、多分「意外」と思われるものを紹介してみたい
15年ほど前に長崎方面を旅行した時に、地元の資料館の方と話をしたときのこと
「“ペッ”と口の外に吐き出した」とは随分きつい言い方だが
これは話をしてくれた女性が根っからの関西人だったためだろう
(そのしばらく前に引っ越してきたばかりだったらしい) 続きを読む
長崎にも当然独特の味覚があるのだろう
その中で、多分「意外」と思われるものを紹介してみたい
「スーパーでゴマ豆腐を買って、食べてみたら甘かったので
思わず“ペッ”と口の外に吐き出したんです」
15年ほど前に長崎方面を旅行した時に、地元の資料館の方と話をしたときのこと
「“ペッ”と口の外に吐き出した」とは随分きつい言い方だが
これは話をしてくれた女性が根っからの関西人だったためだろう
(そのしばらく前に引っ越してきたばかりだったらしい) 続きを読む
2010年08月30日
長崎 夜の中華街 2010年長崎旅行(21)
2010年08月30日
鯛ノ浦教会と福見教会 上五島周遊Ⅳ 2010年長崎旅行(20)
2010年08月27日
頭ヶ島教会 上五島周遊Ⅲ 2010年長崎旅行(19)

上五島の2日目、頭ヶ島へ向かう
頭ヶ島は無人島だったが、幕末のころ迫害を逃れた潜伏キリシタンが移住してきたという
1981年(昭和56年)、島の一角に上五島空港が開港、それに合わせて橋も架かり交通の便が良くなったが
現在空港は閉鎖されているという 続きを読む
2010年08月26日
2010年08月25日
日島曲古墓群 上五島周遊Ⅰ 2010年長崎旅行(17)

福江島を周った翌日、上五島・中通島へ渡る
福江9時20分出航の高速船に乗る

%20650.jpg?psid=1)
(パノラマ写真 写真をクリックしてください 拡大します)
%20650.jpg?psid=1)
(パノラマ写真 写真をクリックしてください 拡大します)
中通島・奈良尾港には9時50分の入港
奈良尾港フェリーターミナルは福江のそれよりもだいぶ小さい
たしか8年前も同じ建物だったように思うが、比較的新しい建物
此処でレンタカーを借り、島巡りを始める 続きを読む
2010年08月25日
福江の武家屋敷通り 福江島周遊Ⅵ 2010年長崎旅行(16)
2010年08月24日
貝津教会と井持浦教会 福江島周遊Ⅴ 2010年長崎旅行(15)

「辞本涯」碑からもと来た道を戻り、貝津教会へ向かう
貝津教会は、外観はさほど特徴は無いように思う
単層の屋根の前方に尖塔(鐘塔)が載った、木造のシンプルな形の建物
もっとも、三沢博昭著の写真集「長崎の教会」の解説では
玄関から二間の部分は増築と判断している(脇にステンドグラスの窓が無い部分)
したがって尖塔も当初のものではないようだ 続きを読む
2010年08月24日
辞本涯 福江島周遊Ⅳ 2010年長崎旅行(14)

福江島を周る、その目的は教会堂巡りなのだが
此処で次の目的地は1200年前の日本の歴史を偲ぶ場所となる
奈良時代終わりからから平安時代にかけて
遣唐使船はこの付近を日本の最終寄港地として立ち寄っていた
第16次(804年)遣唐使船には留学生として唐に渡ろうとしていた弘法大師空海がいた
彼の残した記録「遍照発揮性霊集」には
「死を冒して海に入る。既に本涯を辞して中途に及ぶ 此に暴風帆を穿って戦風舵を祈る。高波漢の沃ぎ短舟裔裔たり。」(碑文より引用)
とある
この「本涯を辞して(日本の涯を辞して)という言葉を取って
「辞本涯」の碑は遣唐使最終寄港地に建てられた 続きを読む
2010年08月23日
水ノ浦教会 福江島周遊Ⅲ 2010年長崎旅行(13)

水ノ浦教会は、楠原教会から10分ほど離れたところにある
木造だが今まで見てきた教会堂と変わらぬ規模を持つ
全体を白く仕上げられ、海を見下ろす高台にある様を
「貴婦人」との愛称があると、どこかで見た気がする

下から見上げるよりは、教会堂の横の高台から
教会堂と海を一緒に視界に入れたとき、「貴婦人」の愛称を納得する事が出来るように思う 続きを読む
2010年08月23日
楠原教会 福江島周遊Ⅱ 2010年長崎旅行(12)

(HDR加工による画像).......
更に海岸線を行く、島を反時計回りで周遊する
途中幾つかの入り江、山道を越え、岐宿町に入る
この付近には楠原、水ノ浦の二つの教会がある
今回の福江島巡りは8年前と同じ道筋になったが
楠原教会だけはその存在を知らず、前回は行かなかった
この辺は海からは離れている、農村地帯だ 続きを読む
2010年08月23日
堂崎教会 福江島周遊Ⅰ 2010年長崎旅行(11)

フェリーターミナルで軽自動車を一日借り、福江島を駆け足で一周する
料金は¥4,500-、他にガソリン代は自費
後で知ったのだが、五島市のレンタカーの中に軽電気自動車の貸し出しがあるそうだ
料金は軽自動車と同じ、但しガソリン代が無いための代わりに「電気料」¥500が別途掛かる
燃料費まで含めれば通常の軽自動車よりも安いのだが、問題は途中での電気の充電
通常フルチャージで走る事の出来る距離は90km、今回私の走行距離は125kmだったので
途中で充電する必要があるのだが、島内にある充電設備は4箇所
私の行程を例にすれば、途中充電設備のある場所に寄ったので、ルートの点では問題なく
おそらく充電もすぐに出来る状況だった
フル充電で所用時間30分だからスムーズに行けばさして問題ない
しかし、話によるとシーズンの最中にはこの充電のために渋滞が起きたという
(もっとも、このときはまだ充電設備が1箇所しかない時の事だったのだが
電気自動車が増えれば同じような問題が起きるだろう)
インフラの整備がまだ十分で無い今の時点では、シーズンオフに借りるのがよいだろう 続きを読む
2010年08月21日
五島 福江島へ渡る 2010年長崎旅行(10)

(HDR加工による画像).......
長崎の宿は大波止のフェリーターミナル近くにとる
明日、高速船の第一便で福江島へ渡るので、朝は少し早い

普通のビジネスホテルだが、窓からは港の景色が見える
束の間の休息の友に、こんな景色もよい 続きを読む
2010年08月21日
紐差教会、生月島と廻る その後長崎に入る 2010年長崎旅行(9)

(パノラマ写真 写真をクリックしてください 拡大します)
宝亀教会を見学した後、直ぐ近くの紐差教会へ行く


紐差教会は規模が大きく、長崎では浦上天主堂の次に大きい
1929年(昭和4年)10月竣工、鉄筋コンクリート造、設計・施工は鉄川与助による
内部が折上げ型の天井となっており、草花の装飾がアクセントとなっている
ただ、内部を木材によるコウモリ天井や彫刻で装飾された中規模の教会堂に比べると
その印象に大味なものを感じてしまうのは致し方ない 続きを読む
2010年08月20日
帆布カバン 喜一澤

旅行の最後の日に京都の「帆布カバン 喜一澤」に行った
また長崎の旅行の記事の順番に割り込む事になるが
このときの印象、感想も早いうちに書き留めておきたかったので、先に書くことにする
(正式名称は「帆布カバン 㐂一澤」で「喜」の漢字が崩した形になっています)
奈良から京都に入り、荷物を預けた後
京都市バス「206」系統に乗る
「知恩院前」バス停で降りると、その近くに「帆布カバン 喜一澤」はある
此処に来た理由は、長年使っていた「一澤帆布」カバンの修理を依頼するため
このカバンは今回の旅行中も酷使していたが、大きな裂け目とショルダーベルトの痛み
そして革のパーツの極度の傷みが目立っていた
(「一澤帆布」カバンの修理を なぜ「信三郎帆布」に出さないのか、という点については後述する)
「帆布カバン 喜一澤」は、7月7日にオープンしたばかり
代表者である一澤喜久夫氏は、かつて「一澤帆布」で作られたカバン・帆布製品の多くをデザインした人だという
私が修理を依頼したカバンも、喜久夫氏によって原型のカバンから改良されたものだそうだ
私が「帆布カバン 喜一澤」に修理を依頼した理由の一つに
このカバンを造り上げた人の店に修理してほしかったという点がある 続きを読む
2010年08月16日
2010年08月16日
8月15日 奈良の夜

長崎の各地を回った旅行後の数日を、今奈良で過ごしている
まだ長崎の旅行の事は、最初の三日目までしか書いていないが
ここで奈良の夜(8月15日)を、今までに記事に割り込む形で書く
長崎での日程を終えて奈良に入ったのは一昨日の13日
奈良は何度も来ている場所だから、今回は余り外を回る事を重視せずに
休息を第一にすることにした
本日(15日)も、午前中に平城宮(大極殿)に出かけたが
その後体調に不安を感じ(熱中症だったかもしれない)
早めに宿に帰り横になる、結局は夕方まで休んでいた
まだ頭痛を感じる体を起こして、東大寺に向かう
春日大社の万燈篭を見るのは諦めたが
東大寺の万灯供養は、私自身灯篭の寄進をしているので見ておきたかった

8月のお盆までの奈良の夜は行事が多いが
多くの観光客を集める「燈花会」は14日で終わる
それでも15日は春日大社の万灯篭と東大寺の万灯供養、そして高円山の大文字焼きがある
したがって東大寺、春日大社付近の人出は多い(東大寺の万灯供養は3時間で3万人が訪れるという)
大文字焼きは京都が本家で有名だが、「大文字」ならばそれ以外にも各地で行われているようだ
高円山の大文字は「日本一大きい」とのふれこみである

8月15日、日本においてこの日は特別な意味を持つはず
元来「お盆」として、亡くなった人のことを思い浮かべる日なのだが
それに加えて「終戦(敗戦、日本以外の国においては“開放”である場合もある)記念日」として認識されている
私個人としては、「8月15日(あるいは8月6日・9日も含めて)」の思いが
「8月」だけで終わってしまうことに危惧を感じる
また「8月15日」が、「せめて一ヶ月前だったら」「半年前だったら」「一年前だったら」と思わずにいられない
このときの戦争では、最後の一年の間に犠牲者の9割が集中しているという
「戦争の記憶を風化させるな」といわれる
「戦争の記憶」は「マイナスイメージ」として「ネガティブ」に喧伝されている(自国のことを悪く言うな)ようにも思えるが
自国の「誤り」を正しく「認識」することは再び戦争をしないためにも必要だと思う
長い日本の歴史の中ではほんの短い期間における「誤り」のために自国の歴史全体が傷つくなどということは
考えなくていいし、歴史から学んだことから行う修正は堂々と行うべきだ
「事実」に対しては常に「謙虚」でありたい


東大寺の万灯供養、灯篭の中の願文には「先祖代々供養」「家内安全」等に混じって
少なくない数の平和への願いが書き込まれている
また「先祖代々」の中にも、多くの戦死者、戦時の犠牲者が含まれている
「8月15日」の持つ特殊性かもしれない


8月の15日に至る一週間の、奈良の夜は美しい
その美しさに誘われて、この時期の奈良を何度も訪れた
去年も訪れていたし、また訪れるだろう
確かに「観光化」かもしれないが、日常から離れていろいろな事を思い浮かべるのに良い機会であるとおもう
「灯火」の揺らめきは、そのことをほのかに思わせてくれる
2010年08月15日
「すめらみくにの乙女たち」

一冊の本を紹介したい
鈴木ひで著 「すめらみくにの乙女たち」
戦時中を女学生として過ごした一人の女性が
得意の絵の才を生かしてその時代を回想した一冊の画文集
8年前の夏、群馬方面を旅行中に
小さな町の資料館の受付に置かれていたのを見つけた
その土地の出身だった女性が書いたという(おそらくは自費出版)
私はもちろん戦争を知らない年代だから
この当時のことは話や当時の資料から想像するよりほかない
またこの本は、この当時の「ある一面」を捉えたに過ぎない
それはこの時代を生きた人でさえ、その時代の全体を把握することは出来ないからだ
しかし、時代の渦中に根ざした視点は大切だ
この本の著者は、この時代の「ある一面」を、この当時の視点で描き出す
そこには、後の時代の判断は加えられていない
あくまでもその時代に「何を考えたか」「何を信じていたか」「何が興味の対称だったか」などを
当時の価値基準を元に焙り出している

そこには私の年代では想像するより他ない、その時代の様相が浮かび上がる
・(男子校生とは)知り合いでも 幼なじみでも
おたがい 口をきいたら校則違反
そして 不良と呼ばれます
・運動会の警備係は
会場に男子校生がいたら
直ちに 先生に通報

しかし
・恋文と言うものが 舞い込んだと 大騒ぎです。
みんなでまわし読みして 大騒ぎ 恋文は ボロ ボロ
誰かが きれいに裏打ちしてきました
このような物は直ちに 担任又は教務室へ提出の事..と
校則にあったけど...。
現代の高校生達がこれを読んだらどう思うだろうか
時代は此処まで人々の意識を締め付けていた
後のエピソードでは、ホッとさせるような微笑ましさもあるが
今の時代から振り返れば割り切れないものもある
人の生活に道徳は大切だが、それは内面の問題のように思う
道徳が「強制された思想」とすり替えられていた時代だったという事だ
(そのような時代の復活を今の世の人々は望むだろうか?)

もちろんこの本に「戦場の悲惨さ」は無い
「戦場」に比べたら何かしらの「余裕」もあっただろう
しかし、そのような「余裕」を自己規制させるような雰囲気が、おそらくはかもし出されていただろう
そのような自己規制は現在だって垣間見る事が出来る
ある時には「自粛」という言葉が世間を覆ったことがある
また別の時には「自己責任」という言葉に惑わされた時がある
どちらも最近だという事をどれだけの人が意識しているだろうか
そのほかの、雰囲気に時代が「なんとなく」流された例など数多い
「バブル」「郵政選挙」「与野党逆転」「今のご時勢」・・・・・
「あの当時」よりも遥かに情報が多く、自分で考える事が出来るはずなのに
判断を「他にまかす」「流れにまかす」という世情は現代でも確実にある
「あの時代の事」をあの時代を過ごしてきた人が語る時
「国にだまされた」
と、口癖のように言う
「あの時代」、全てのものを、「人の心」までも戦争に総動員しようとした
その様子の、ある田舎町でのありさまがこの本の中でも描かれている
しかし、そうした中で御しえない「人の心」の部分が
「一寸した反抗心」と、時折見せる「ほほえましさ」「小さなことへの憧れ」の中に盛り込まれているように思う
しかしそうしたものも、大勢の中では飲み込まれていくより他ない
最初は良く縫われていた「千人針」さえも
物資の不足で、やがて縫われることも無くなった
そのような「些細な」事からも国の状況をうすうすと感じながらも
大勢には飲み込まれていくより他無かった
そんな様子が書き込まれている
この時代を生きてきた人たちには、自身の体験した事をその時の眼差しで語ってほしい
そうした「語り」の貴重な一例がこの本だと思う
次の記事及びホームページもご参照ください
03/09/09付毎日新聞記事より
戦時下の女生徒の日常生き生きと--画家・鈴木ひでさん、中央区で個展 (「すぎもと画廊」ホームページ内)
鈴木ひでweb展覧会(「キララ★あがつま」ホームページ内)