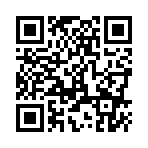2011年01月28日
360度パノラマムービー
駿府城東御門 枡形 360度パノラマムービー
前回の記事と同じ素材を使って360度パノラマムービーを作ってみた
時々商業施設などのホームページで画像にポインターを当てて動かすと
画像がグルグルと回るものを見かけるが
それと同じものになる
続きを読む
2011年01月26日
円周魚眼による駿府城東御門
2011年01月21日
円周魚眼視界の試み

静岡駅南口ペデストリアンデッキよりサウスポットを見る 画角173°
(写真をクリックしてください 拡大します)
「円周魚眼視界の試み」と題してみたものの
一言で言えば「魚眼レンズで撮った写真」とほぼ同じ物となる
しかしここで扱う写真には「魚眼レンズ」を使用していない
コンパクトカメラによる多数枚の画像の合成となる
手間の掛かる画像作成となり、「魚眼レンズ」そのもので撮ったほうが手っ取り早いのだが
わざわざこのために魚眼レンズを手に入れるつもりも無いため
手持ちのカメラを使いパノラマ撮影の延長として試みてみた 続きを読む
2011年01月17日
クラリネットはだんだん小さくなっていった
美しい音楽が鳴り響いていた
旋律は滑らかに歌い
弱い音から強い音まで自然に変化する
歌っているような、いや自在に喋る様な楽器による音楽
その楽器はクラリネットだった
この日使われたクラリネットは”バセットクラリネット”というのだそうだ
普通のクラリネットより1オクターブ下まで音が出せるという
音楽が言葉になっている人による「演奏」
モーツァルトのクラリネット協奏曲の演奏だった
拍手の後でアンコール
シュタイナーという作曲家の「だんだん小さく」という曲
何が”小さくなる”のか?
だんだん音が小さくなっていき、最後は消え入るように終わる?
そのようにも考えたが
実際には、もっと「物理的」な問題だった 続きを読む
旋律は滑らかに歌い
弱い音から強い音まで自然に変化する
歌っているような、いや自在に喋る様な楽器による音楽
その楽器はクラリネットだった
この日使われたクラリネットは”バセットクラリネット”というのだそうだ
普通のクラリネットより1オクターブ下まで音が出せるという
音楽が言葉になっている人による「演奏」
モーツァルトのクラリネット協奏曲の演奏だった
拍手の後でアンコール
シュタイナーという作曲家の「だんだん小さく」という曲
何が”小さくなる”のか?
だんだん音が小さくなっていき、最後は消え入るように終わる?
そのようにも考えたが
実際には、もっと「物理的」な問題だった 続きを読む
タグ :音楽
2011年01月16日
”一万歩”歩く

歩数を数えるカウンターの事を万歩計と言うことがある
(「万歩計」は登録商標で一般には「歩数計」なのだそうだ)
以前は歩数計を持ち歩いていたのだが
電池が切れてからそのままにしていて
一日に何歩あるくかについて、しばらくの間頓着していなかったのだが
ここ最近血液検査等で脂肪等の数値が悪くなってきたため
電池を入れなおしてまた使うようにしたのだが
歩数計を持っていなかった時は、歩くこと自体に意識していない事に気が付いた
「歩数計」またの名を「万歩計」の「万歩」
一口に「一万歩」といってもどのくらいの距離があるのだろうか
一日での合計で「一万歩」だとどのくらいの距離を歩いたかについてはっきりと意識できない
例えば歩数計で「5km」と出ていたとしても
一日の中で分割しての5kmはどのくらいの距離なのか分かりづらい 続きを読む
2011年01月15日
ベートーヴェン 交響曲第7番
ベートーヴェンの交響曲第7番は
「あだ名」こそ付いていないが、他の有名曲に劣らぬ人気があるようだ
私がこの曲を知ったのは、山本直純さんの番組「オーケストラがやって来た」でこの曲を取り上げた事からなのだが
その番組では特に第二楽章のアレグレットを集中的に解説していたことを覚えている
鮮明なリズム感と快活さにあふれた曲だが
第二楽章アレグレットの沈痛さが良いアクセントになる
そして、色々なタイプの演奏を受け入れる事の出来る曲のように思う
-・-・-・-・-・-・-
私は一時期へルマン・シェルヘンの指揮による演奏をよく聴いていた
(管弦楽はルガノ放送交響楽団)
いくあまた有る録音の中でも特に速い演奏の一つだったが
その演奏の真剣さと管弦楽の演奏技術の危なっかしさ
時折聴こえる指揮者の掛け声など
「演奏に熱中している」ことが手に取るようにわかるような
独特の熱気にあふれていた
-・-・-・-・-・-・-

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮:カール:ベーム
(ポリドール POCG-3155 1975年3月16日 NHKホール)
しかし、私の世代の日本の音楽愛好家なら
1975年のベーム/ウィーン・フィルによる伝説の来日公演での演奏を取り上げるかもしれない
私自身は75年のベーム/ウィーン・フィル来日公演はほとんど記憶がない
ベームの死後放送されたそのときの録音を聴いてもあまりピント来なかった
後年発売されたそのときの模様を記録したCDを今改めて聴くと
金管の強奏に特徴を感じさせられるのだが
テンポ自体はインテンポを貫いた、非常に落ち着いたもののように思われる
ベームの演奏全般に言えることなのだが
音楽は常に「正しいテンポ」と「正しい音の鳴り方」をしている
デフォルメをしない、と言う訳ではない
時に行われる金管の強奏やテンポの動きに違和感を感じないのだ
それは75年の演奏にも、後で述べる他の二つの演奏にも言える
ただ、75年の演奏は「高揚」という意味で少し物足りないようにも思える
-・-・-・-・-・-・-

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮:カール:ベーム
(Altus ALT065 1980年10月6日 昭和女子大学 人見記念講堂)
ベームは日本に合計4回来ているが
そのうち75年と80年に第7番を指揮している
私の記憶に残っているのは80年の演奏なのだが
このときは一ファンとしての敬愛を感じながらもそのテンポの遅さに対して幾ばくかの戸惑いもあった
ベームはその翌年8月に亡くなっており
日本での演奏は公開の場での最後の演奏となったそうだ
そのときの演奏も現在CD化されている
今その演奏をあらためて聴きなおすと、意外なことに「遅さ」を感じない
たしかに「恰幅のよい」演奏であり、そのテンポは踏みしめるような重みがあるのだが
音楽は生気を感じさせる
安心して聴く事の出来る演奏であり
終楽章の終わり部分はテンポは堂々としていても内から湧き出る熱気が迫ってくるような気がする
重い石が大きなエネルギーを持って悠然と迫ってくるようなものだ
若い頃「遅い」と感じたテンポが今になってさして遅さを感じずに受け入れる事の出来るようになったのは
私自身が重ねてきた「年のせい」のためなのだろうか
世評とは違うが、私には75年の演奏よりも80年の演奏のほうが良いように思う
-・-・-・-・-・-・-

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮:カール:ベーム
(METEOR MCD-12 1977年10月8日 ベルリン)
話は前後する
私がベームを聴き始めたのは77年の来日がきっかけだったのだが
それからと言うもの、FM放送で「海外の演奏会」でのベームの演奏が流れると
それを欠かさずカセットテープにエアチェックしていた
その中にベートーヴェンの交響曲第7番がどのぐらい含まれていたか、記憶はあやふやだが
ある一つの演奏は強く印象に残っていた
1977年10月8日にベルリン・フィルを指揮した演奏だった
現在の基準からすればこれも「遅め」のテンポなのかもしれないが
私には中庸と思えた
貧しい音質のカセットテープ録音を繰り返し聴いた中から感じ取られたのは
特に終楽章の異様な熱気
曲の終わり近くでは、あのベルリン・フィルのアンサンブルが乱れるほどに
ベームがオーケストラを煽り立てたように聴こえる
あの学生の頃
カセットテープすら乏しい小遣いの中から買っていた頃
粗末なモノラルの学習用カセットデッキのスピーカーに耳をこすりつけて聴いていた頃に
常に思っていたこと
「もっと良いチューナーが有ったら、もっと良い録音機があったら」
セピア色の記憶はもっと鮮明に残っていただろう
しかし、私にとって幸運な事があった
以前にも書いたことがあるが、これらの放送された思い出の演奏の内のいくつかは
輸入盤のCDとして市販されていた
この演奏も市販されていた
秋葉原のショップでこのCDを見つけたときの満たされた思いをよく覚えている
そして記憶は鮮やかに甦った
そのCDを久しぶりに聴いてみた
テンポは中庸であっても全体に活気があり
特に「あの」第4楽章の熱気は間違いの無い物だった
第4楽章は先に進むにしたがって熱を帯びてくる
私には微妙にだが音楽がだんだん加速していくように思えた
そう考えなければこの音楽の熱の帯び方を説明できないように思えた
そこで時計を見ながら実際に一分間の拍数を数えてみたところ
出だしの1分間に144に対して終わりでは154だった
一割増しにも満たない加速だったが
恐らくは、オーケストラの面々も実際の加速以上の「圧力」を感じたのかもしれない
その「圧力」が聴くほうにもまたとない「高揚」を感じさせたように思える
これが「枯れた」といわれるベーム晩年の演奏の一つだった
もちろん演奏会ごとのムラは有ったかもしれないが
このような演奏も知っていたから
よく言われるような、晩年は「枯れた」(生気を失った)演奏だというベームへの評を私は今でも信じてはいない
-・-・-・-・-・-・-
ベートーヴェンの交響曲第7番は有名曲であると共に人気曲でもあるから
実演で聴く機会も多い
私が唯一ウィーン・フィルを生で聴いた時も
曲目はこの曲だった(指揮はアーノンクール)
ベームとアーノンクールでは音楽は違う筈なのだが
例えば金管の音に、ベームのときに響いた音と同じように聴こえた時
音信の途絶えていた友人と再会したような懐かしさを感じた
しかしながら、ヴィヴラートをかけない弦の響きには
「これがウィーンフィルの弦の音なのだろうか?」という戸惑いも感じた
このことについては、別の指揮者による演奏を聴く機会があれば確かめてみたいと思うのだが
これ以降、まだウィーン・フィルを生で聴いた事は無い
-・-・-・-・-・-・-
今週の日曜日にはまたこの曲を演奏会で聴く
静岡の室内オーケストラだが、どのような演奏になるだろうか
「あだ名」こそ付いていないが、他の有名曲に劣らぬ人気があるようだ
私がこの曲を知ったのは、山本直純さんの番組「オーケストラがやって来た」でこの曲を取り上げた事からなのだが
その番組では特に第二楽章のアレグレットを集中的に解説していたことを覚えている
鮮明なリズム感と快活さにあふれた曲だが
第二楽章アレグレットの沈痛さが良いアクセントになる
そして、色々なタイプの演奏を受け入れる事の出来る曲のように思う
-・-・-・-・-・-・-
私は一時期へルマン・シェルヘンの指揮による演奏をよく聴いていた
(管弦楽はルガノ放送交響楽団)
いくあまた有る録音の中でも特に速い演奏の一つだったが
その演奏の真剣さと管弦楽の演奏技術の危なっかしさ
時折聴こえる指揮者の掛け声など
「演奏に熱中している」ことが手に取るようにわかるような
独特の熱気にあふれていた
-・-・-・-・-・-・-

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮:カール:ベーム
(ポリドール POCG-3155 1975年3月16日 NHKホール)
しかし、私の世代の日本の音楽愛好家なら
1975年のベーム/ウィーン・フィルによる伝説の来日公演での演奏を取り上げるかもしれない
私自身は75年のベーム/ウィーン・フィル来日公演はほとんど記憶がない
ベームの死後放送されたそのときの録音を聴いてもあまりピント来なかった
後年発売されたそのときの模様を記録したCDを今改めて聴くと
金管の強奏に特徴を感じさせられるのだが
テンポ自体はインテンポを貫いた、非常に落ち着いたもののように思われる
ベームの演奏全般に言えることなのだが
音楽は常に「正しいテンポ」と「正しい音の鳴り方」をしている
デフォルメをしない、と言う訳ではない
時に行われる金管の強奏やテンポの動きに違和感を感じないのだ
それは75年の演奏にも、後で述べる他の二つの演奏にも言える
ただ、75年の演奏は「高揚」という意味で少し物足りないようにも思える
-・-・-・-・-・-・-

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮:カール:ベーム
(Altus ALT065 1980年10月6日 昭和女子大学 人見記念講堂)
ベームは日本に合計4回来ているが
そのうち75年と80年に第7番を指揮している
私の記憶に残っているのは80年の演奏なのだが
このときは一ファンとしての敬愛を感じながらもそのテンポの遅さに対して幾ばくかの戸惑いもあった
ベームはその翌年8月に亡くなっており
日本での演奏は公開の場での最後の演奏となったそうだ
そのときの演奏も現在CD化されている
今その演奏をあらためて聴きなおすと、意外なことに「遅さ」を感じない
たしかに「恰幅のよい」演奏であり、そのテンポは踏みしめるような重みがあるのだが
音楽は生気を感じさせる
安心して聴く事の出来る演奏であり
終楽章の終わり部分はテンポは堂々としていても内から湧き出る熱気が迫ってくるような気がする
重い石が大きなエネルギーを持って悠然と迫ってくるようなものだ
若い頃「遅い」と感じたテンポが今になってさして遅さを感じずに受け入れる事の出来るようになったのは
私自身が重ねてきた「年のせい」のためなのだろうか
世評とは違うが、私には75年の演奏よりも80年の演奏のほうが良いように思う
-・-・-・-・-・-・-

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮:カール:ベーム
(METEOR MCD-12 1977年10月8日 ベルリン)
話は前後する
私がベームを聴き始めたのは77年の来日がきっかけだったのだが
それからと言うもの、FM放送で「海外の演奏会」でのベームの演奏が流れると
それを欠かさずカセットテープにエアチェックしていた
その中にベートーヴェンの交響曲第7番がどのぐらい含まれていたか、記憶はあやふやだが
ある一つの演奏は強く印象に残っていた
1977年10月8日にベルリン・フィルを指揮した演奏だった
現在の基準からすればこれも「遅め」のテンポなのかもしれないが
私には中庸と思えた
貧しい音質のカセットテープ録音を繰り返し聴いた中から感じ取られたのは
特に終楽章の異様な熱気
曲の終わり近くでは、あのベルリン・フィルのアンサンブルが乱れるほどに
ベームがオーケストラを煽り立てたように聴こえる
あの学生の頃
カセットテープすら乏しい小遣いの中から買っていた頃
粗末なモノラルの学習用カセットデッキのスピーカーに耳をこすりつけて聴いていた頃に
常に思っていたこと
「もっと良いチューナーが有ったら、もっと良い録音機があったら」
セピア色の記憶はもっと鮮明に残っていただろう
しかし、私にとって幸運な事があった
以前にも書いたことがあるが、これらの放送された思い出の演奏の内のいくつかは
輸入盤のCDとして市販されていた
この演奏も市販されていた
秋葉原のショップでこのCDを見つけたときの満たされた思いをよく覚えている
そして記憶は鮮やかに甦った
そのCDを久しぶりに聴いてみた
テンポは中庸であっても全体に活気があり
特に「あの」第4楽章の熱気は間違いの無い物だった
第4楽章は先に進むにしたがって熱を帯びてくる
私には微妙にだが音楽がだんだん加速していくように思えた
そう考えなければこの音楽の熱の帯び方を説明できないように思えた
そこで時計を見ながら実際に一分間の拍数を数えてみたところ
出だしの1分間に144に対して終わりでは154だった
一割増しにも満たない加速だったが
恐らくは、オーケストラの面々も実際の加速以上の「圧力」を感じたのかもしれない
その「圧力」が聴くほうにもまたとない「高揚」を感じさせたように思える
これが「枯れた」といわれるベーム晩年の演奏の一つだった
もちろん演奏会ごとのムラは有ったかもしれないが
このような演奏も知っていたから
よく言われるような、晩年は「枯れた」(生気を失った)演奏だというベームへの評を私は今でも信じてはいない
-・-・-・-・-・-・-
ベートーヴェンの交響曲第7番は有名曲であると共に人気曲でもあるから
実演で聴く機会も多い
私が唯一ウィーン・フィルを生で聴いた時も
曲目はこの曲だった(指揮はアーノンクール)
ベームとアーノンクールでは音楽は違う筈なのだが
例えば金管の音に、ベームのときに響いた音と同じように聴こえた時
音信の途絶えていた友人と再会したような懐かしさを感じた
しかしながら、ヴィヴラートをかけない弦の響きには
「これがウィーンフィルの弦の音なのだろうか?」という戸惑いも感じた
このことについては、別の指揮者による演奏を聴く機会があれば確かめてみたいと思うのだが
これ以降、まだウィーン・フィルを生で聴いた事は無い
-・-・-・-・-・-・-
今週の日曜日にはまたこの曲を演奏会で聴く
静岡の室内オーケストラだが、どのような演奏になるだろうか
タグ :音楽
2011年01月12日
洞慶院の蝋梅 (2011年)

新聞で洞慶院の蝋梅が咲き始めたとの記事を見たのはつい先日のことだった
正月になると、母親が友人から蝋梅の枝をもらってくる
それを玄関前に活けるのが毎年の恒例になっている
艶の有る花から香る甘く芳しい匂いは
一枝の僅かな数の花からも十分に感じ取れる 続きを読む
2011年01月11日
ライトアップされた巽櫓(2)

(パノラマ写真 写真をクリックしてください 拡大します)
同じタイトル名で記事を書いたのは去年の7月だった
あの時は始終さざ波の立った水面に対して長い露出をする事によって
すりガラスを透かして見たような巽櫓の姿を撮ったが
内心は水面の揺らぎの無いときに、もっとシャープな線を見せる巽櫓の水面に映る姿を捉えてみたいと思っていた
先日、少彦名神社へ行った帰りの夕暮れ時に駿府城へ寄った
日中に比べれば静かかもしれないが
走り抜ける車、ジョギングをする人々など
まだ周囲は活動している
しかし寒さゆえだろうか、お堀に住む鯉は身を縮め
水面近く、静かに漂っていた
その時撮った写真だが、去年よりは幾らか良い写真が撮れた
風は静まっていたが、実際にはこのときも水面は動いており
前回よりも輪郭線はハッキリしたもののまだシャープな線ではない
あくまでも「前回よりは良い、次回はもっと良いものを」という意味での途中経過の写真としたいが
恐らくは、これよりも水面が静まる機会は更に少なくなるだろう
だが、そのような機会を気長に待って見たいと思う
2010年7月5日記事 「ライトアップされた巽櫓」
2011年01月10日
少彦名神社の干支彫刻
2011年01月05日
根場(4)

根場は美しい富士山を見る事の出来る土地の一つだと思う
たしかに根場の茅葺屋根住宅は「新築」であり
生活感の無いという意味では「人為的」かもしれない
しかし、40年以上前には確実にこの地で兜造りの茅葺屋根民家が軒を連ねていて
その中に富士山を望む景観が作られていたのであり
その民家群が一夜にして失われてしまったという悲劇的な出来事も思うと
私はこの「新築」兜造り住宅群も過去に連なるものだと考えている 続きを読む
2011年01月02日
浅間神社と久能山東照宮で「うさぎ」を捜す

浅間神社も、久能山東照宮も、建物は多数の彫刻で飾られている
それらの彫刻はそのほとんどが「縁起物」
そのような中には「干支」にちなんだ彫刻もある
それならその彫刻群の中に今年の干支である「兎」も有るに違いない
極めて単純な発想だが
初詣も兼ねて「兎」を捜しに出かけた 続きを読む