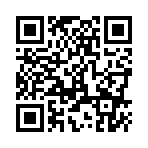2010年03月27日
ブルックナー 交響曲第8番

学生の頃からブルックナーの曲は聴いていたが
初めの頃は理解不能な、馴染めない音楽だった
私にとって「馴染んだ音楽」とは、具体的な旋律なり響きが頭の中に
確固たる記憶として残ることのように思う
その意味で、ブルックナーの曲は「頭の中に記憶されること」を拒むような無骨さがあったように思う
音楽を「好きな音楽」と「嫌いな音楽」に二分することは出来るかもしれない
しかし実際にはその「好きな音楽」と「嫌いな音楽」のそれぞれが更に幾つかの階層に分かれている
例えば「嫌いな音楽」の場合、「理解不能で今後とも遠慮したい音楽」と
「理解しがたい音楽だがどこか気になる、この音楽を自分の物にしてみたい」
と思わせるような曲に分かれるようだ
私が学生の頃は、まだ「ブルックナー・マーラー」と言う風に
余り共通点の無い二人の作曲家を「同時代のワーグナー親派」と言うだけでひと括りにするような
乱暴な論調がまだあったように思う
(ちょうど「ハイドン・モーツァルト」とひと括りにするのと同じような物)
学生の頃からマーラーはよく聴いており、好きな曲も多かった
ブルックナーを聴いてみようと思ったのは、この乱暴な論調を鵜呑みにして
マーラーに近い作曲家と理解してブルックナーに近づこうとしたからだと思う
実際には「取り付く島の無い」ブルックナーの音楽に何度も跳ね返されることになるのだが
ブルックナーについては「別に聴かなくとも良い」と思いながらも
実際には何度もトライしていた
実のところ、ブルックナーは今もって「好きな作曲家」とは言いがたいように思える
よく聴く曲は第7番・第8番・第9番の三曲に時々第5番に手が伸びる程度
これらの曲は好きだが、そのほかの曲も同じように好きとは言えないしまったく聴く気にならない
ブルックナーの全体に対してはまだ私には壁があるように思う
そうした中で最初に頭の中に記憶されてきたのは第8番だったように思う
と言っても、何か劇的なことがあって好きになったわけではない
たぶんFM放送をエアチェックしたテープを繰り返し聴いているうちに馴染んできたのではないだろうか
ブルックナーの音楽は「オルガン的な響き」とか「ゴシック建築」に喩えられたりする
いずれにせよ、何かを描写するような音楽ではないし、旋律線に乏しいようにも思う
聴き始めた当初は「力づくで作られた曲」という印象を持ったものだ
その代わりその場その場の響きに関心が向くようになればかなり楽しめるのではないだろうか
-・-・-・-・-・-・-
ブルックナー 交響曲第8番 ハ短調
指揮:スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ
読売日本交響楽団
(2010年3月26日 サントリーホール)
この日の演奏会は指揮者スクロヴァチェフスキさんの読売日響常任指揮者としての最後の演奏会となっている
ただ、86歳と高齢ではあるものの「退任」であって「引退」ではない
事実10月にはまた来日するそうだ
しかし演奏会場の雰囲気は少し違いがあるようだ
それは登場時の拍手、終演後の熱狂的な拍手に現れている
開演10分前の舞台上には何人かのオーケストラ団員が楽器を吹きながら調整をしている
その頃から楽団員は三々五々と少しづつ舞台に現れ始め、開演時になって残りの大多数の団員が入場する
そして、舞台が少し落ち着いてから最後にコンサートマスターが一人登場して会場からの拍手を受ける
この最後にコンサートマスターが一人で登場する慣わしはいつから行われるようになったのだろうか
もちろん今でも他の楽団員と一緒にコンサートマスターも登場する以前からの登場の仕方をする楽団もあるが
最近ではこの様なコンサートマスターの登場の仕方が多くなっているように思う
この方法、私は余り好きではない
そして指揮者の登場
交響曲第8番はヴァイオリンのトレモロをバックに低弦が旋律を弾くことで開始される
このヴァイオリンを始めとする弦のトレモロは全曲を通して土台となる
このトレモロがウネリとなり、管の強奏が加わると音楽は地響きのような迫力を生む
管の強奏といっても、実際には管の音は突出していなかったように思う
あくまでも弦のウネリに乗るような形で管が添えられている、と言う風に聴こえた
もしCDを聴いただけでこの曲を語ろうとしたら
「チェロが旋律を受け持つことが多い」と書いたかもしれない
しかし一寸した新発見があった
「たとえばこの緩徐楽章(ベートーヴェンの交響曲第五番第二楽章)はどのように始まっていたか?‥‥‥‥
オーケストラで弾いた経験のある人ならば即座に答えられるが、一般の人ならばチェロが旋律主題を担当していたと答えるのが精一杯のところだろう」
この文章は当日配布されたプログラム(と言っても80ページある小冊子)の中に書いてあった
当日の曲目とは無関係のエッセイの中にあった物だった
問題の部分は、実際にはヴィオラとチェロのユニゾンで旋律主題が弾かれていたのだが
開演前にこの文章を読んだときには、一寸した驚きと共に「運命」に対して一つ知識を得たぐらいにしか考えなかった
ところがブルックナーの交響曲第8番の演奏が始まってふと気が付くと
今までチェロが旋律を弾いていたと思っていた箇所の大半が
実はヴィオラとチェロがユニゾンで旋律を弾いていたことに気が付いた
よくその響きを聴いてみれば、チェロ単独での響きよりも少し鄙びた様な響きをしている
私にとってこの事は演奏会を「見に行って」初めて判ったことだった
また、第一楽章および第二楽章については
旋律を弾く(吹く)楽器の音が「美しく響いていない」様に思えた
ヴァイオリンが旋律を弾くときは低音域で力強く弾くことが多いように思えたし
木管が旋律を吹くときは、背景に何かベールが掛かったような響きがしていた
その「ベール」はティンパニの弱音のトレモロであったり、あるいは金管の低音の持続音で有ったりしたのだが
この曲が「見た目の美しさ」を求めていないことを示しているのだろう
「旋律を弾く楽器の美しさ」は、第三楽章以降になってヴァイオリンの音が高音の方向に突き抜けるようになったり
管楽器の旋律の背景から「ベール」が取れたりした時に初めて感じられるようになった
これは曲全体がもやもやした中から徐々に明るい方向へ突き抜けていこうとする
「高みへの志向」プログラムを持っているからだろう
また曲の中に、随所に上昇音階が現れることも同じ傾向を示しているように思える
たとえば第三楽章後半で上昇音階が弦から金管に受け継がれて
上り詰めたところで金管のファンファーレと打楽器の打ち鳴らされる部分などがそうだ
そして第四楽章は快速テンポ
指揮者は晩年になるとテンポが遅くなるというが
スクロヴァチェフスキさんにはその様な印象は受けない
テンポに活気があるだけでなく、リズムにも微妙ながら緩急の変化があるようだ
安定した音楽作りなのだが、目立たない所で「闊達自在」なのではないだろうか
「枯れた演奏」ではなく「円熟した演奏」なのだろう
管弦楽が強奏する場面でもうるさく絶叫するような印象はなく
全ては安定した弦(この曲では弦の「うねるような」トレモロが曲の多くの部分を支えている)の上に
他の楽器が乗っているようであり、特に金管楽器がスタンドプレーに走るようなことは無い
今実演で聴くことの出来る最も安定したブルックナーの演奏なのだろう
%20650.jpg)
(パノラマ写真 写真をクリックしてください 表示された画像をもう一度クリックすると拡大します)
「サントリーホール」というホールの印象はあっても
「サントリーホール」という建物の印象は希薄だ
それは建物としてのボリュームを全体像として感じることが出来ないからだが
サントリーホールの周囲を含めた景観は面白い
其処には「都会的」な洗練された物を感じる
タグ :音楽