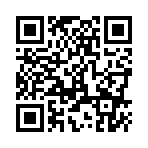2012年06月29日
ベルワルド 交響曲第三番「サンギュリエール」
「面白いけれど、つかみどころのない曲」なのか
「つかみどころのないけれど、面白い曲」なのか
しかし、第一楽章最初の音が出た瞬間から引き寄せられる
「めっぽう面白い曲」なことは確か
曲の始まりは一小節ごとに「ド」「レ」「ミ」「ファ」「ソ」と言った具合に
オクターブ以上を上昇していく
その一音ごとに、その音の周りを簡素に装飾していくだけ
「”ドレミファソラシド”の上昇音階に装飾をつけて、短い曲を作りなさい」と言った練習課題のようにさえ聴こえる
まことにつまらない曲の始まりの筈なのに
その単純な上昇音階を包み込む「周りの音」が簡素ながらも魅力的に聴こえる
そして、その「周りの音」はふくよかに膨らんでいく
それは「穏やかな日の出」
その日の出は、夏のギラギラした太陽でもなく
冬の寒さに凍える中に見るものでもなく
「春の穏やかさ」をもっている
そんな雰囲気に誘われて、ついつい30分足らずの全曲を聴き通してしまう
でも、第一楽章を聴き終えたとき
「メロディーは何処にあったんだろう?」と考え込んでしまう
動機(短い旋律)を積み重ねたパズルのような曲のよう
形が捉えにくいから「つかみどころがない」
けれど「面白い曲」、聴いていてワクワクする
第二楽章は「ドラ焼き」
二枚の皮(ゆっくりとした音楽)の間に餡子(スケルツォのような軽快な音楽)がはさまれている
「コロンブスの卵」的なアイディアの音楽
第三楽章は、今までの明るさ、穏やかさとバランスをとるかのように
少し暗さを帯びた、速い音楽
しかし最後では明るいファンファーレで終わる
聴き終わってみると、第一楽章の印象が際立っているように思う
ベルワルドというあまり知られていないスウェーデンの作曲家
音楽界の中心から離れていたからだろうか
自分の好きなように音楽を組み立てることが出来たのだろうか
実験精神旺盛なのだが
それを越えて第一楽章は魅力に満ち溢れる
目の届かないところに、魅力的な音楽はまだ多く隠されているようだ
「つかみどころのないけれど、面白い曲」なのか
しかし、第一楽章最初の音が出た瞬間から引き寄せられる
「めっぽう面白い曲」なことは確か
曲の始まりは一小節ごとに「ド」「レ」「ミ」「ファ」「ソ」と言った具合に
オクターブ以上を上昇していく
その一音ごとに、その音の周りを簡素に装飾していくだけ
「”ドレミファソラシド”の上昇音階に装飾をつけて、短い曲を作りなさい」と言った練習課題のようにさえ聴こえる
まことにつまらない曲の始まりの筈なのに
その単純な上昇音階を包み込む「周りの音」が簡素ながらも魅力的に聴こえる
そして、その「周りの音」はふくよかに膨らんでいく
それは「穏やかな日の出」
その日の出は、夏のギラギラした太陽でもなく
冬の寒さに凍える中に見るものでもなく
「春の穏やかさ」をもっている
そんな雰囲気に誘われて、ついつい30分足らずの全曲を聴き通してしまう
でも、第一楽章を聴き終えたとき
「メロディーは何処にあったんだろう?」と考え込んでしまう
動機(短い旋律)を積み重ねたパズルのような曲のよう
形が捉えにくいから「つかみどころがない」
けれど「面白い曲」、聴いていてワクワクする
第二楽章は「ドラ焼き」
二枚の皮(ゆっくりとした音楽)の間に餡子(スケルツォのような軽快な音楽)がはさまれている
「コロンブスの卵」的なアイディアの音楽
第三楽章は、今までの明るさ、穏やかさとバランスをとるかのように
少し暗さを帯びた、速い音楽
しかし最後では明るいファンファーレで終わる
聴き終わってみると、第一楽章の印象が際立っているように思う
ベルワルドというあまり知られていないスウェーデンの作曲家
音楽界の中心から離れていたからだろうか
自分の好きなように音楽を組み立てることが出来たのだろうか
実験精神旺盛なのだが
それを越えて第一楽章は魅力に満ち溢れる
目の届かないところに、魅力的な音楽はまだ多く隠されているようだ
タグ :音楽